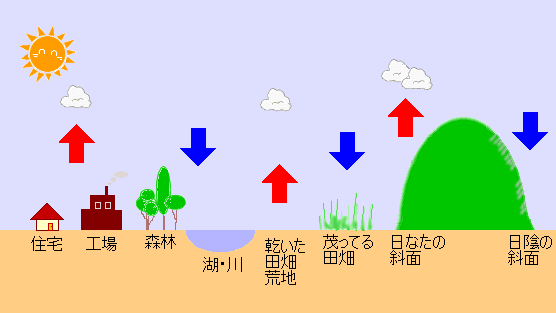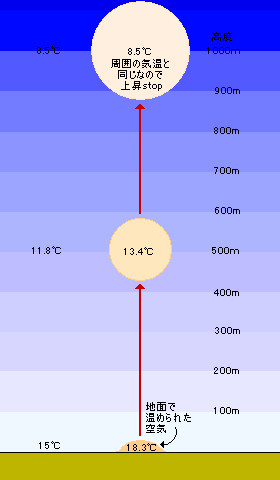風
風の強さ
| 風力階級 |
風速 |
吹流しの状態 |
地上の様子 |
| 0 |
0〜0.2m/s |
 |
煙はほぼまっすぐ昇る。ほとんど無風。 |
| 1 |
0.3〜1.5m/s |
 |
煙のなびき方で風向がわかる。 |
| 2 |
1.6〜3.3m/s |
 |
顔に風を感じる。木の葉が動く。
キャノピーのエアインテークが動き始める。 |
| 3 |
3.4〜5.4m/s |
 |
木の葉や小枝が絶えず揺れる。
キャノピーにテンションを掛けると簡単に開く。 |
| 4 |
5.5〜7.9m/s |
 |
砂埃が舞い上がり、紙片が舞い上がる。
キャノピーがバタつく。フライトをやめた方が無難。 |
| 5 |
8.0〜10.7m/s |
 |
葉のある木が揺れ始め、山鳴りが聞こえ始める。
エリアクローズ。 |
サーマル(上昇気流)とシンク(下降気流)の発生源
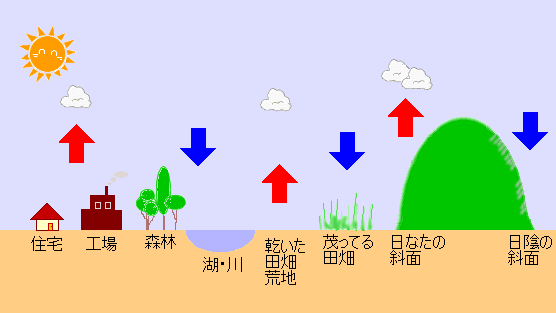
サーマルが発生するには、地面で温められた空気が何かのきっかけで地面から剥がれ上昇し始めます。しかし、そのサーマルは風に流されているので、実際には発生源の真上にあるわけではありません。平地から山に向かって風が吹いているとすれば、サーマルも山沿いに流されます。そうしたサーマルが集まる山沿いや山の頂上を狙った方が効率よく上げられます。また、斜面に沿って上がってくる途中でサーマル同士がくっついて、大きなサーマルに成長することも期待できるのです。
太陽に面した南斜面は平地に比べると同じ面積の当たりの受ける熱エネルギー量が大きいので、温まりやすくサーマルが発生しやすい。その為、ほとんどのテイクオフの場所は南斜面に作られている事が多いのです。
| サーマル上昇の理屈 |
サーマルは、上昇しながら自分自身の温度を下げていきます。
これは、空気の温度は上昇するにつれて膨張していきます。なぜなら上空に行くほど気圧が低くなるため、周囲から押さえつけられる力が弱くなります。
気圧が低いと膨張する現象は、街中で買った菓子袋を持って山に行くと、袋がパンパンに膨れ上がってる事で実感できることでしょう。
そして膨張するにつれて気温は低くなっていきます。
この時の温度の下がる割合は、積雲の雲底より低いところ、つまり水蒸気がまだ凝結していなければ、100m上昇するごとに約1度ずつ下がります(乾燥断熱減率)。
周りの空気よりもサーマルの方が冷え方が大きく、周囲の気温と同じになるまで上昇を続けるのです。
1000m上昇すれば9.8℃下がるので例の場合では
18.3-9.8=8.5℃
となるのです。
その為、例の場合では高度1000mでサーマルの上昇は頭打ちとなります。
一方、水蒸気が凝結したサーマル、つまり積雲の中では、気温や気圧によって変わるものの、100m上昇につき大体0.4〜0.8度の割合で下がります(湿潤断熱減率)。
いずれにしてもサーマル自身の温度の変化は周囲の温度変化に関係なく、特に乾燥断熱減率は一定なのがポイント。 |
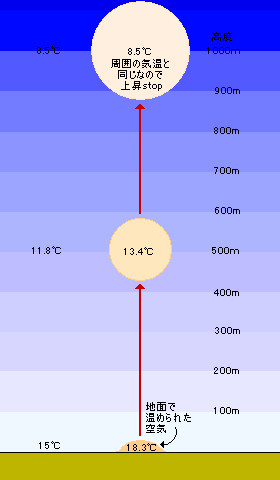 |